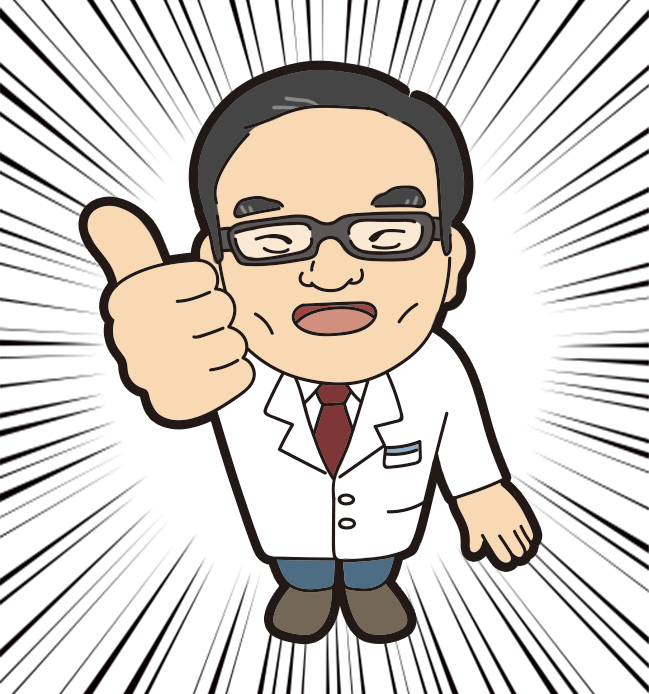遠絡療法の基礎知識と用語・記号
身体(Body)の活動が、生命(Life)です。
医療とは、連続する身体の営み(Life Flow)の調和を再建する術です。

遠絡療法が考えるライフフローとは
- 血液・リンパの流れ
- 神経の伝達・反射
- 臓器の代謝など
気(生命エネルギー)の流れ
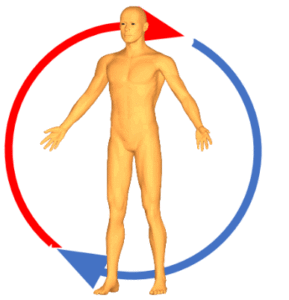
東洋医学で表現されている概念
病態をパイプ内の流れでイメージしたモデル
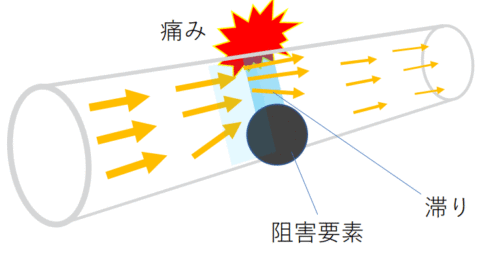
接経 ~七つの治療法~
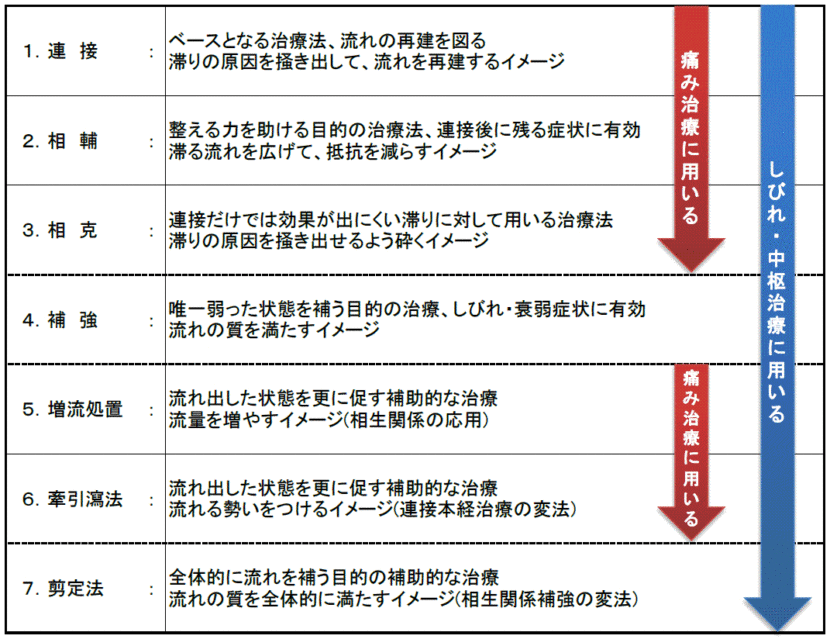
子午流注~流れを再建する基礎理論
生命の営みすべては、気(生命エネルギー)の流れが存在する事と密接に関係している。
この観点から身体の不調は流れの滞りが起きていると考える。
各流れは補い合う性質があり、その規則性を応用して治療するのが遠絡接経の連接である。
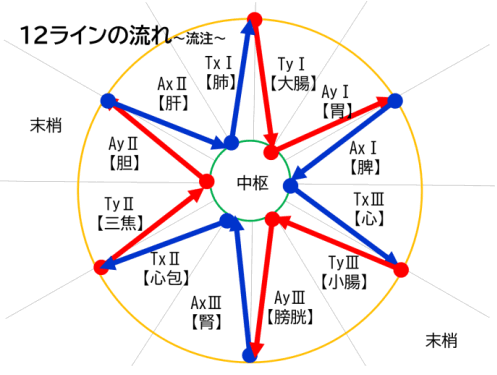
ラインと表記について
身体を26本の流れ(ライン)が循環しており、頭頚部にはその26本が全てある。
14種類26本のラインは、特性が異なる2つの分類がある。(奇脈と12ライン)
12ラインは上肢と下肢に6ラインずづ走行し、それぞれに陰経と陽経のペアがある。
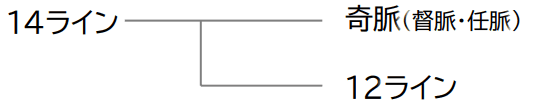

ラインと経絡の対比
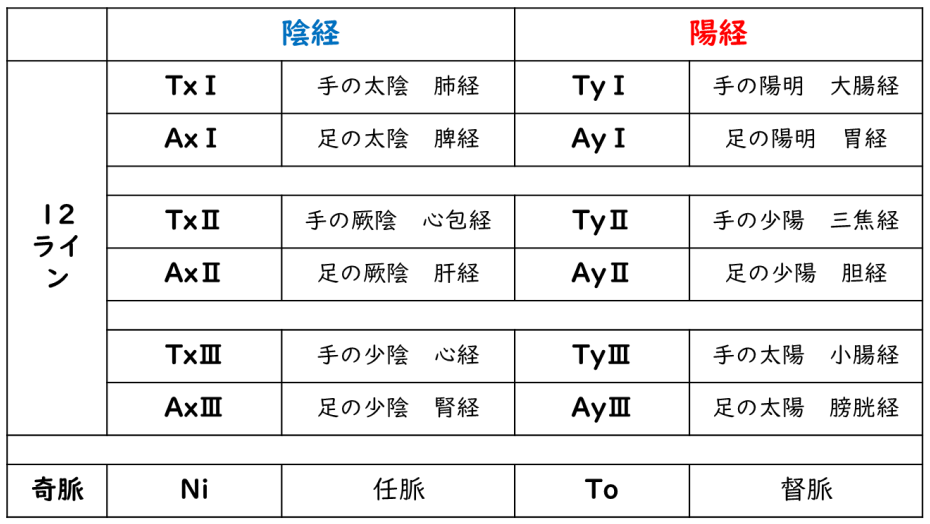
ラインの記号化の規則
- 上肢へ走行するライン:T(Te;手)
- 下肢へ走行するライン:A(Ashi;足)
- 陰経:x 陽経:y
- 前⇒後、橈側⇒尺側:Ⅰ⇒Ⅱ⇒Ⅲ
治療の組み立て方 ~肩こり編~
①片方の肩こりで、頸肩の筋肉が硬くなっているケース
見解≪局所≫筋肉レベルの問題
⇒はっきりとした生活動作内で原因が分かっているケースは、症状を訴える筋肉へのアプローチを考える。
②両方の肩こりで、頸肩の筋肉が硬くなっているケース
見解≪中枢≫脳・神経レベルの問題
⇒首肩の筋肉は延髄にある副神経の支配で調整されている。
大元の調整力からの治療ができる。
③ひどい肩こりを感じているが、頸肩の筋肉は硬くなっていないケース
見解≪中枢≫脳レベルの問題
⇒首肩の筋肉自体は凝りを起こしていないのに不快な感覚を意識させれているのは、脳の奥にある間脳の問題、肩凝りだけなく自律神経症状など他の症状も併発しているケースも多いがまとめての治療ができる。

④頸肩の筋肉はひどく硬くなっているが自覚症状がないケース
見解≪中枢≫未病 脳レベルの問題
⇒首肩の筋肉の凝りよる不快症状に順応し、無知覚状態となっている。遠絡療法では陰経と陽経が病的なつり合いを持っていると考える。循環の低下が中枢機能の不足を招き、負の蓄積が無知覚下で進行していく。飽和度を超えた時点で他の症状が表面化する可能性を秘めている。未病状態の一つと考える。この負の要素を改善させる治療ができる。
遠絡療法では、治療の方針を立てる際に“局所”と“中枢”の区別を持って行っている。
末梢(局所)はその部位だけで成立しているのではなく、中枢部からの影響を受けて成り立っている。
また、意識は脳で起きる反応である。
よって、訴える症状に対し、3つの関係を踏まえて治療を立案する。
①局所のみの処置
②中枢のみの処置
③中枢の調整を踏まえて、局所への処置